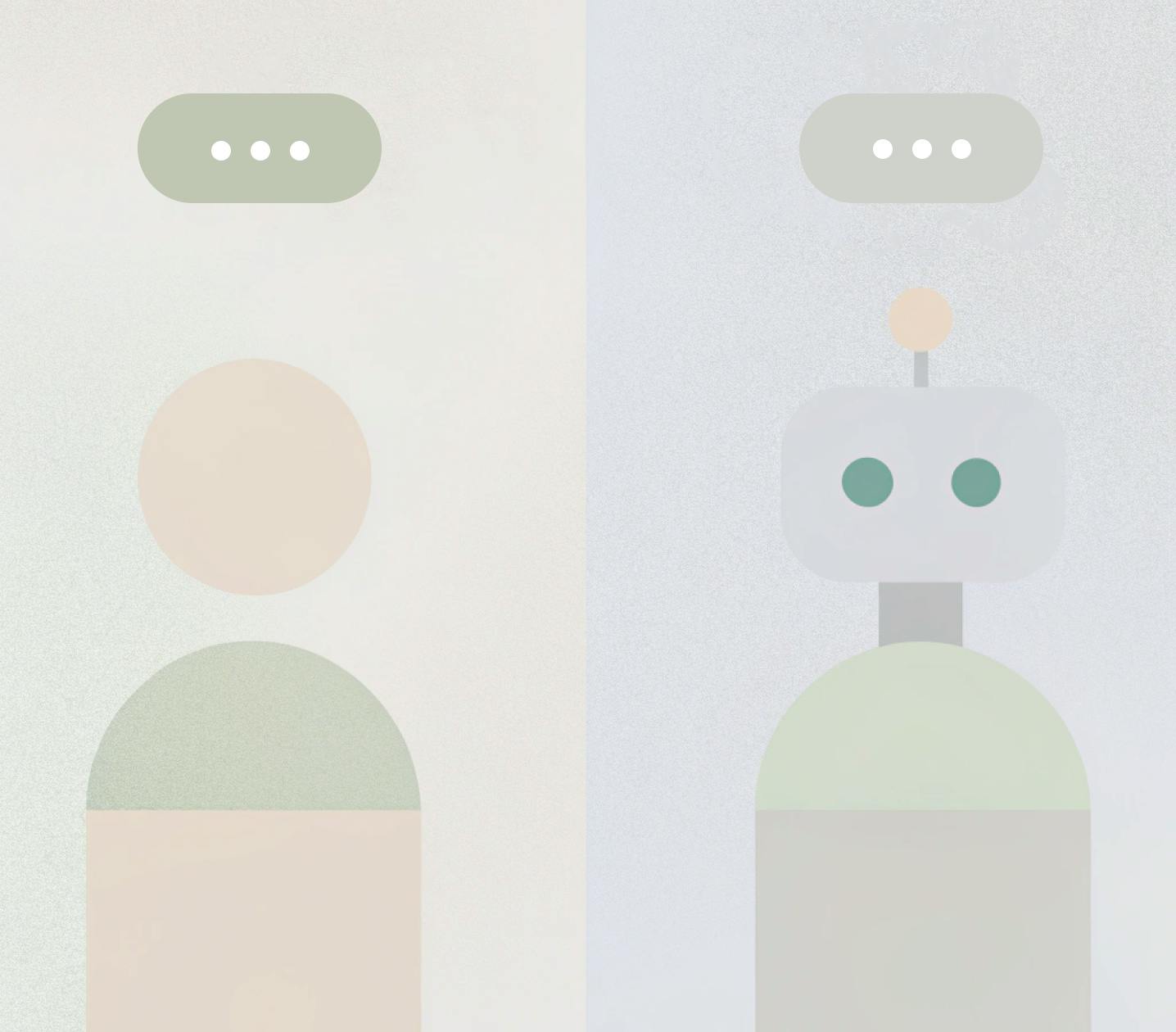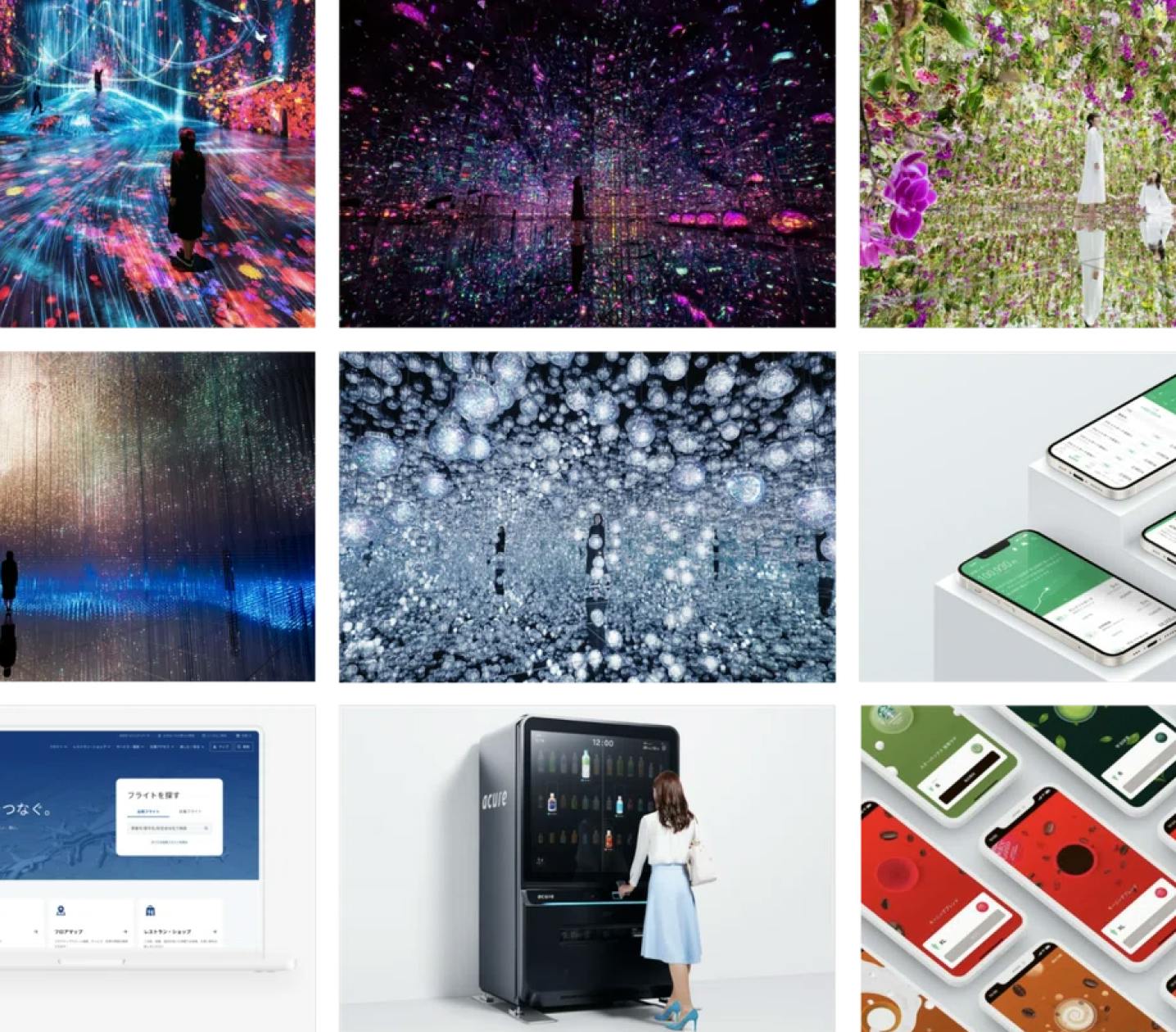オンラインでファッションアイテムを購入する際、自分にぴったりのものを選ぶのは難しいと感じている人は多いのではないでしょうか。それを裏付けるかのように、「やっぱり違う」と返品する人が後を絶ちません。
この状況を改善しようと立ち上げられたのがオランダ発の「style + code(スタイル・アンド・コード)」です。AIを使って、消費者の商品選びをサポートするツールを提供しています。その具体的な内容や、背景にあるデザイン思考などについて、共同創業者兼ディレクターのJelle Stienstra(イェル・スティンストラ)さんに話を聞きました。

Jelle Stienstraさん
返品を減らすためのカスタマイズ
―― ファッションECでは返品が多いという問題があるようですね。
欧州のファッションECでは、「サイズやスタイルや色が合わなかった」といって、毎日大量の商品が返品されています。返品率はアイテムによって20-70%に上ります。
��そして悲しいことに、ECは非常に低マージンのビジネスが多いので、返品された商品を再販するよりも廃棄した方が安上がりだということで、多くの商品が処分されています。
―― 商品が廃棄されているというのはもったいないですね。「style + code」が提供する解決法は?
まず、これを解決するためには、パーソナライゼーションが必要だと思っています。それには3つの形が考えられます。
ひとつは、完全なカスタムメイド。その人だけの特別なものを生成(ジェネレート)するものです。これは靴だったら3Dプリンターなどで可能になるかもしれませんが、ファストファッションのような分野ではまだ実現できません。
2つ目は、セミ・カスタマイゼーション。例えば、消費者が基本となる服をもとに、色やロゴをカスタマイズできるというもので、これはすでに多くの企業が取り入れていますよね。
そして3つ目は、すでに市場に出回っている膨大な数の商品の中から、消費者にぴったり合うものを見つけること。これが私たちのサポートしているパーソナライゼーションです。
―― これだけたくさんの商品が出回っているのだから、自分にぴったりの商品があるはずだと。
そうですね。自分に合った商品が見つかれば、返品を減らすことができるでしょう。
これにはもうひとつの側面があって、ブランド側が商品を作りすぎているという問題もあります。小売業者やブランドが消費者のニーズをより深く理解できれば、過剰生産をせずに的確な方向で製造することも可能になるでしょう。
AIと人間の選択を融合
―― 具体的にはどのように商品選びをサポートするのですか?
基本的には、メガネ、靴、アパレル商品を見つけるのをサポートするAIソリューションを提供しています。分かりやすい例で、メガネを挙げましょう。
まずはメガネの写真を撮影し、コンピュータービジョン(コンピューターが画像や動画などの視覚データから情報を導き出せるようにするAIの分野)を使ってその形状を検出し、フレームの上下のライン、色の微妙なニュアンスまでを分析します。
そして、��同じ手法を消費者にも適用します。私たちは小売店向けのシンプルなツールを彼らのウェブサイトやオンラインショップに導入して、消費者がアドバイスを求めたときに、「AIデジタルスタイリスト」と呼ばれる機能を働かせます。これは、実店舗のスタイリストのように、消費者の顔を分析して最適なアドバイスを提供するものです。
消費者には「照明を付けてください」「メガネを外してください」「髪が顔にかからないようにしてください」といったガイドラインが伝えられ、その後、彼らにセルフィー(自撮り写真)を撮影してもらいます。ここでもコンピュータービジョンが活用され、眉毛の形や目と目の距離、顎のラインや肌の色などが分析されます。
―― そこで顔の形状に合ったメガネがマッチングされるんですね?
はい。でも、AIの選択だけに頼るわけではありません。特に大規模AIモデルは膨大なデータをもとに学習しているため、最終的なアウトプットは「平均的」なものになりがちで、個別のニーズや独自性には対応しきれません。また、さまざまなバイアスが絡む危険があり、完全に信頼できるものではありません。
そのため、私はここに独自のデザイン思考を取り入れたAIモデルを開発し、訓練しています。色彩をより深く理解し、スタイルをより的確に把握し、異なる視��点を持つAIモデルです。
具体的には、私たちはここに人間のスタイリストの判断を取り入れました。彼らに8万通りのメガネと顔のコンビネーションを見せ、それぞれの組み合わせが「調和している」か「表現力が豊か」か「繊細」かを評価してもらったのです。彼らは何が美しくマッチするかという理論や一般的なデザインの法則を学んでいますし、的確なコンビネーションを選ぶことができます。
そこで、メガネの形状と消費者の顔の分析をもとに、まずは5つのメガネが推薦されます。

style + codeによる「AIデジタルスタイリスト」が、セルフィーから顔の特徴を分析し、パーソナライズされたメガネを提案。
―― まずは自分に似合うものが5つに絞られる。大分選びやすくなりますね。
しかも単なる「おすすめ」だけではなく、眉毛の形やあごのライン、顔色とのコントラストなどをもとに、なぜその5つが選ばれたのか、�消費者に説明します。このプロセスがあることで、消費者はその根拠を理解し、より自信を持って商品を選択できるようになります。
しかし、その5つの選択は単に消費者の顔の特徴に合う「安全な」ものです。最終的にはそこに「あなたはどういう人ですか?」という、パーソナリティを加えることが大切になります。そこで、私たちは消費者がスライダーを左右に動かして、好みを選択できるようにしました。これは自分の顔に投影されたメガネの画像を見ながら操作できるようになっています。
例えば、デフォルトではニュートラルな状態ですが、左に動かせばより控えめなデザインになり、右に動かせばより個性的で力強いデザインになる……というように。
私たちは結局、人のためにデザインしています。だから、コンピューターに人の主観的な感覚や感情も考慮させることを試みているのです。

style + codeの「AIデジタルスタイリスト」が、顧客の個性や顔の特徴に合ったメガネ選びをサポート。
―― このサービスはすでにオランダで導入されているのですか?
はい。オランダでは「Hans Anders(ハンス・アンダース)」というチェーン店で導入されています。ほかにもドイツ、フランス、ボリビア、インドネシアにも顧客がいます。このサポートで売り上げが3倍に増えたという実績もあるんですよ。
学術界からビジネスの世界へ、デザイナーが影響力を持つために学んだこと
―― AIを使って客観的な審美眼と個人の主観的な感情を組み合わせるのは、面白い試みですね。ここに至るまでのJelleさんのご経歴を教えてください。
私はオランダのアイントホーフェン工科大学で工業デザインを学んでいたのですが、ある時点から「現象学」に興味を持ち始めたんですよ。現象学というのは、「人はそれぞれがユニークな存在であり、意味とは客観的なものではなく、人と対象との相互作用の中で生まれるものである」という哲学です。
例えば、ここにある椅子。なぜ椅子なのでしょうか?ある人は「座れるから」と言うでしょう。でも小さな子供からみたら「山」かもしれないし、今ここで火事が起これば、「窓を割るもの」かもしれない。それが意味するのは、自分の身体との関係なのです。
私はこの哲学に惚れ込み、博士課程ではこの哲学をデザイン思考やデザインに取り入れることを研究していました。
―― 現象学を取り入れて、どのようなものを作りましたか?
例えば、スピードスケート用のスケート靴の下に装着し、滑り方を測定するデバイスです。スピードスケートでは刃の角度が正しくなければ適切な力を発揮できませんが、「シューッ、シューッ」というスケートの音をフィードバックとして返すことで、スケーター自身がその足の運びや刃の角度の良し悪しを判断できるようにしました。
ほかにも柔らかいパンと硬いパンを焼き分けるトースターなど、哲学とテクノロジーを融合させて、美しいものをたくさん作りました。
でも、ある時点では私は「学術の世界から離れなければならない」と思い始めたのです。大学で製作していたのはとても興味深いものでしたが、非常に高価で、誰も買わないものばかりでしたから。

Jelle Stienstraさんによる「Augmented Speed-Skate Experience」。プロのスピードスケーターがリアルタイムで自らの動きや力の使い方を音で聞くことで技術を向上させる。
―― そして、その後はビジネスの世界へ。
はい、私は戦略コンサルティング会社のマネジメント・コンサルタントとなり、アウディやポルシェ、Ahold(オランダの最大手スーパーマーケット「アルバートハイン」の親会社)、Douwe Egberts(オランダのコーヒーブランド)など、さまざまな小売業者やブランドのイノベーションを支援し、AIやブロックチェーン、3D技術など、幅広い分野に携わりました�。
商業の世界に身を置くことで気付いたのは、使う言語が違うということです。私はデザイナーとしてはしっかり訓練されてきたけれど、少なくとも自分のトレーニングの中では、「ビジネスのボキャブラリーで説明すること」を学んでいなかったと気づいたのです。
―― コミュニケーションの仕方が違うということですか?
結局のところ、CEOやチーフマーケティングオフィサー、つまりブランドや小売業の意思決定をする人たちと話すときには、哲学とか現象学とか、UXなどのデザイン用語は全部忘れなきゃいけないんですよ(笑)。アイデアを伝えるためには、「コスト削減」や「利益になる」という話をしないといけない。本当にインパクトを与えたいなら、こうした言葉を学ぶ必要があると思います。
例えば、アウディのプロジェクトでVR(仮想現実)のポップアップストアを作ったとき。 新しい車が自分の頭上を飛んでくるように見えたり、VRの中で試乗できたり、それはもうリアルすぎて、ほぼレザーの匂いまで感じるレベルでした。
これは、現象学的な視点からいうと、その世界に没入してプロダクトとインタラクションできる体験を提供するということなんですが、マーケティングの観点から見ると、ポップ�アップストアを使うことで、物理的な小売店舗を減らせるというのがポイントでした。 だから、ビジネス的には「素晴らしい体験」ではなく「コスト削減」が一番重要な要素だったんですよね。
―― なるほど、それはビジネス界での経験を経てはじめて気づいたことだったのですね。その後のキャリアは?
そのアウディのポップアップストアに取り組んでいたとき、一緒にプロジェクトに関わっていた「PTTRNS.ai」という3DとAI技術の会社に誘われて、そこに加わることにしました。そして、6年間そこで働いた後に独立して、今年「style + code」を立ち上げたところです。
アカデミックなキャリアでは「デザインの哲学」とか、「異なるデザイン手法」などを学び、マネジメントコンサルティングの世界では、実践的なビジネスの視点をを身に着けました。今はちょうど人、テクノロジー、ビジネスの3つを組み合わせられる立場にいるんじゃないかな、と思っています。
―― style + codeのサービスにはまさに、技術とビジネス以外にJelleさんの哲学的なバックグラウンドが活かされていますよね。
そうですね。結局、人ってみんなユニークだし、モノとの関わり方も違うし、世界の見え方も人それぞれ違う。そ�ういう理解は自分の哲学的なバックグラウンドから来ていて、「パーソナライゼーションが大事だ」という考えにつながっているのだと思います。
日々の業務で株主やクライアントとやりとりするときには、そんな話はしないで、ビジネス的な文脈で話をしますけど、結局のところ大事なのは、「それをどうデザインのソリューションに落とし込むか」なんですよね。デザイナーはそうやって、もっと多くのインパクトを世の中にもたらすことができると思いますよ。
フリーランスライター。日本、中国、マレーシア、シンガポールで主にライター・編集者として活動した後、2004年よりオランダ在住。同国の生活・教育・イノベーション・デザインを雑誌やオンラインメディア、ラジオなどで紹介するほか、オランダと日本を結ぶさまざまな活動を手がける。著書に『週末は、Niksen。』(大和出版)。
https://www.yamantextfactory.com/