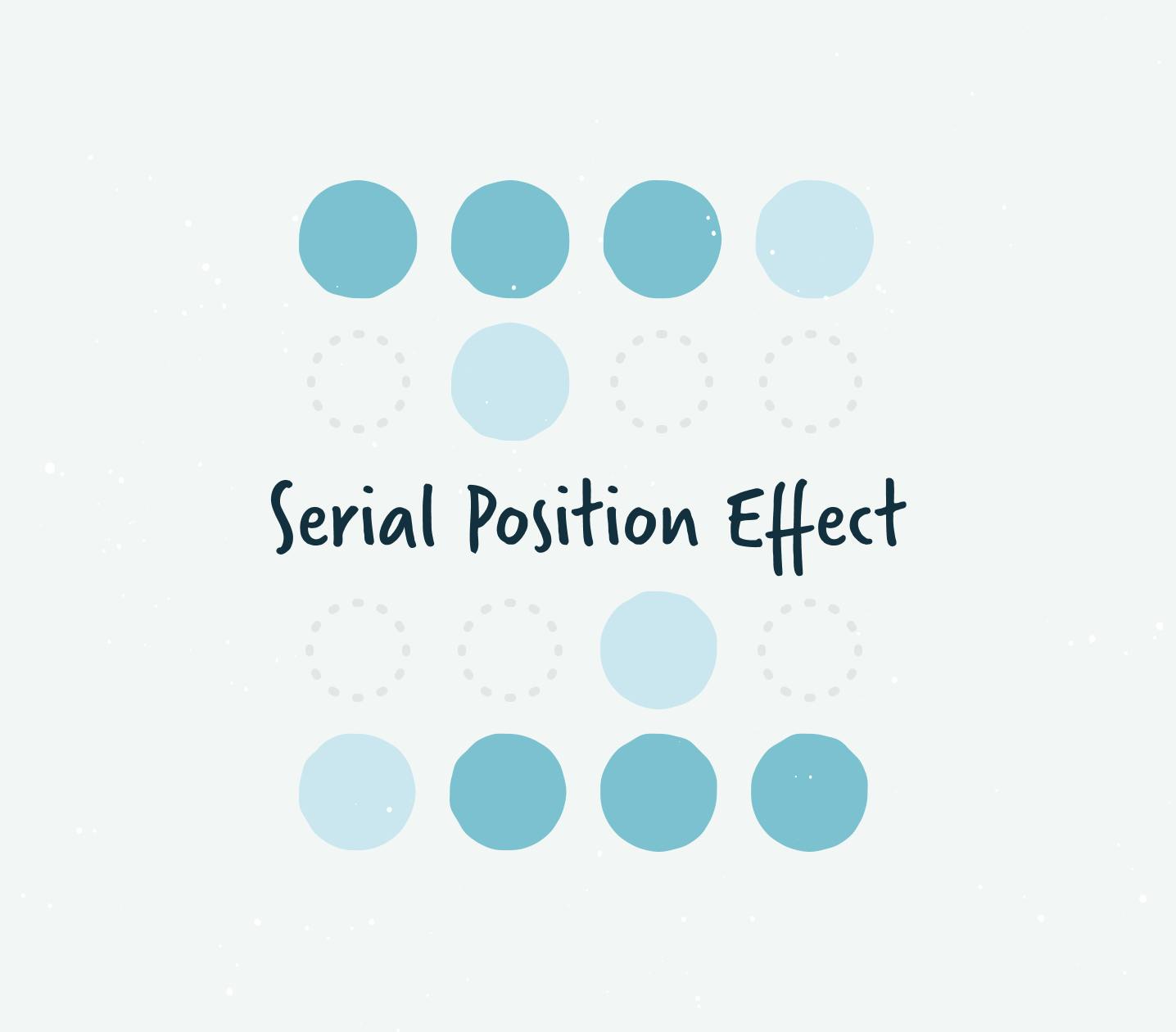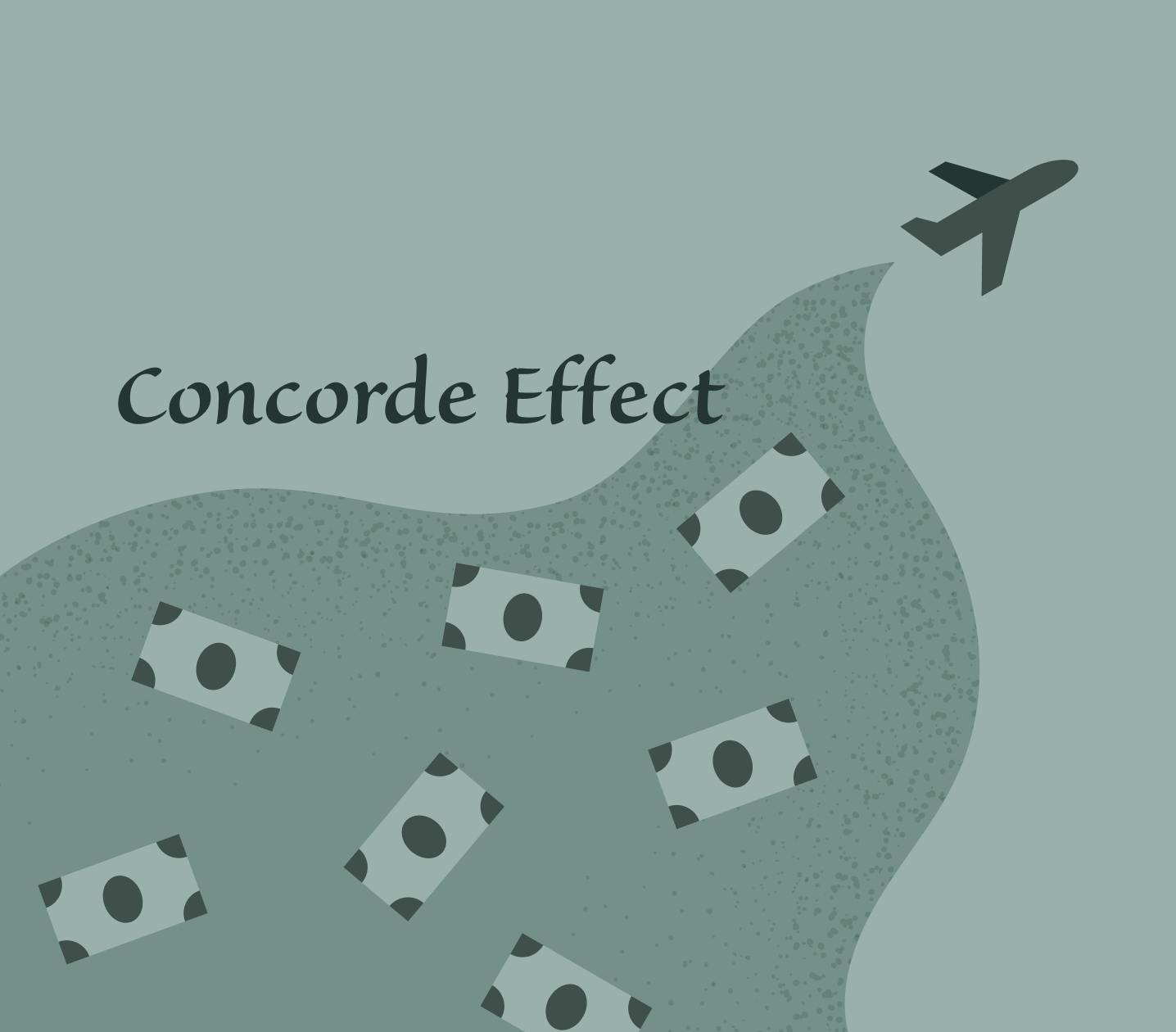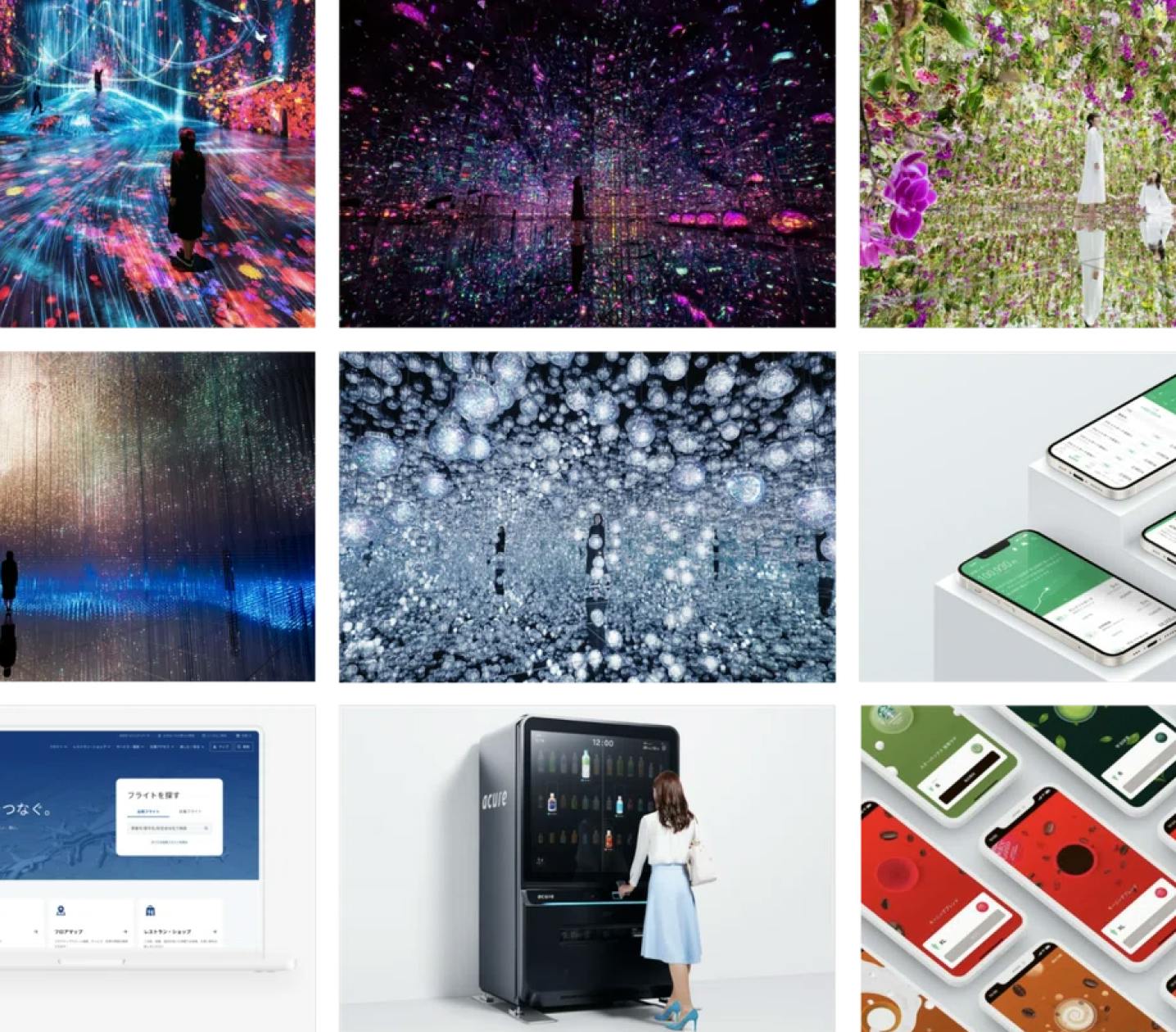ゲインロス効果とは?
ゲインロス効果とは、相手に対して初めにネガティブな印象を与えた上で、後からポジティブな印象を与えると、最終的な評価が強くポジティブなものになりやすいという現象です。1965年に、エリオット・アロンソンとダーウィン・リンダ�ーが発見しました。
具体的には、怖く見える人と話してみたら、実は優しい人だったことが分かって、好感度がぐっと高まることなどが挙げられます。いわゆる「ギャップ萌え」のようなものと紹介されることが多いです。
ただし、もともとゲインロス効果は、他者からの評価の変動に着目した実験が起源となっており、単なるギャップによる好印象について述べられた現象ではありません。
- ゲインロス効果とは?
- 相手に対して初めにネガティブな印象を与えた上で、後からポジティブな印象を与えると、最終的な評価が強くポジティブなものになりやすいという現象。
また、ゲインロス効果は、「ゲイン」と「ロス」の2つの心理効果を合わせて、ゲインロス効果と呼ばれています。ゲイン効果は、評価者からの一貫性のある好意的な評価よりも、初めは否定的な評価を受けて後に好意的な評価を得た場合、被評価者はより魅力的に感じるという効果です。
一方のロス効果は、ゲイン効果とは逆の効果で、初めに好意的な評価を受けた後に否定的な評価を受けると、評価者に対する印象が悪くなりやすいという効果を指します。
つまり、ネガティブな印象からポジティブな印象になる場合だけでなく、ポジティブな印象からネガティブな印象になった場合に、ネガティブな印象がより強調される効果も、ゲインロス効果の1つというわけです。
ゲインロス効果の実験結果
エリオット・アロンソンとダーウィン・リンダーが行ったゲインロス効果の実験をご紹介します。実験では、80名の女子学生が被験者となりました。まず、被験者の女子学生(以下、女子学生A)は、実験室に呼び出された後、実験者から以下のように説明されます。
今からもう一人女子学生(以下、女子学生B)がやってくること
2人に「実験のサポート役」と「被験者役」をそれぞれ担当してほしいこと
今この部��屋にいる女子学生Aには「実験のサポート役」になってもらうこと
上記の説明では、女子学生Aには後から来る女子学生Bが被験者だと思わせていますが、実際は、女子学生Aが真の被験者として実験されています。女子学生Bは、事前に言動を指定された「サクラ」です。しかし、女子大生Aはそのことを知らされていません。
女子学生Aが上記の説明を受けた後、もう一人の女子学生Bが実験室に来ます。そして、実験者は、女子大生Aだけに、以下2つの作業を7セットするよう指示しました。
2人で会話すること
女子大生B(サクラ)と実験者の会話を、女子大生Aが盗み聞きすること
2番目の作業では、1番目の会話における女子大生Aへの評価を女子大生Bが実験者に打ち明けます。真の被験者である女子大生Aは、その様子を盗み聞きしています。その内容には、以下の4つの条件が仕掛けられていました。
最初から最後までポジティブな評価
最初から最後までネガティブな評価(悪口を言う)
最初はポジティブな評価を言うが、最終的にはネガティブな評価(ロス条件)
最初はネガティブな評価を言うが、最終的にはポジティブな評価(ゲイン条件)
具体的なポジティブ・ネガティブな評価の内容は以下の通りです。
上記の実験後、真の被験者である女子大生Aは、自分のことを好き勝手言ってた女子大生Bに対して、21段階の評価(とても好き〜非常に嫌い)を行いました。その結果は、以下の通りです。
上記の結果から、最初にネガティブな印象を与えてからポジティブな印象を与えると、好印象が増す傾向があることが分かりました。
同時に、4つの条件の中で、女子大生Bへの印象が最も悪くなったのは、3の「最初はポジティブな評価を言うが、最終的にはネガティブな評価(ロス条件)」の場合でした。この場合は「ロス効果」が働き、最初にポジティブな印象を与えた後にネガティブな印象を与えると、ネガティブな印象がより強調されることが示されています。以上、2つの効果を合わせてゲインロス効果と呼びます。
ゲインロス効果の具体例: 交渉戦術の「良い警官・悪い警官」
「良い警官・悪い警官」とは、尋問などに使用される心理的戦術のことです。具体的には、攻撃的・否定的な態度の質問者(悪い警官役)と、共感的・支援的な質問者(良い警官役)の質問者が、対象者に対してそれぞれ相反するアプローチを行い、良い警官役の質問者は、悪い警官役の人から対象者を庇うようにします。
上記のアプローチを行うことで、悪い警官役の質問者への恐怖・良い警官役の質問者への信頼感が芽生え、結果的に良い警官に情報を話すよう促すといった戦略です。
ある実験では、「良い警官」役の人が、交渉においてどれだけ効果的なのかを調査しました。被験者はまず、「あなたは今、あなたの将来に関わる大切なプロジェクトに参加していて、他のメンバー2人から、そのプロジェクトに関する論文の執筆を促されている」と説明され、この時点で論文執筆を受け入れる確率を聞きます(状態A)。
その後被験者は、「良い警官・悪い警官」に対応した4種類の方法で、2人のメンバーから以下のような説得を受けました。
メンバー2人とも被験者の気持ちを尊重してくれる(受容-受容)
メンバー2人とも被験者の気持ちを尊重してくれない(拒否-拒否)
被験者の思いを尊重してくれないメンバーが説得(拒否)してから、被験者の思いを尊重してくれるメンバーが説得(受容)
被験者の思いを尊重してくれるメンバーが説得(受容)してから、被験者の思いを尊重してくれないメンバーが説得(拒否)
上記の結果、被験者が説得される前の(状態A)よりも、メンバーの要望を受け入れる確率が高まった方法は、「拒否→受容」の順番になっている3番目の方法でした。
つまり、最初に被験者の思いが拒否されたネガティブな印象が基準となったことで、その後のポジティブな印象が際立ち、要望を受け入れやすくなったことが証明されたのです。
以上のように、交渉戦術の「良い警官・悪い警官」の例は、��ゲイン・ロス効果と同じ構造だということがわかります。
類似の心理効果「ハロー効果」との違い
ゲインロス効果と似ている効果に、「ハロー効果」があります。ハロー効果とは、あるものを対象としたとき、その対象の目立った特徴に引っ張られて、他の特徴の印象が変化する効果です。例えば、一般的には説得力がない内容の話であっても、専門家や実績のある人が話すことで、説得力が増す現象などが挙げられます。
ゲインロス効果とハロー効果は、どちらとも印象形成に影響を与える心理現象です。しかし、「ネガティブな印象→ポジティブ→ポジティブな印象が強調」「ポジティブな印象→ネガティブ→ネガティブな印象が強調」となるゲインロス効果とは違って、ハロー効果は、対象の特定の特徴が全体の印象に影響を与えます。
ゲインロス効果とハロー効果の違いを簡単にまとめると、以下のようになります。
|
ゲインロス効果の注意点: 最初のイメージを下げすぎると効果がない
ゲインロス効果の1つとして、最初にネガティブな印象を与えてからポジティブな印象を与えることで、ポジティブな印象が強調されることが挙げられます。
しかし、過度に最初の印象を下げると、ネガティブな印象が強く残り過ぎて、嫌悪感を持たれてしまう可能性があります。実際に、心理学者のアッシュの研究で「初頭効果」という効果が証明されています。初頭効果とは、第一印象が後の評価に影響するといった効果です。
したがって、最初の段階で相手に強い嫌悪感を持たれてしまうと、その後どんなに良い印象を残そうと努力しても、ゲイン効果を発揮できなくなる可能性が高いというわけです。そうならないためにはマイナスとプラスの幅は大きくし過ぎず、最初の印象を下げすぎないように注意する必要があります。
まとめ
ゲインロス効果は、初めに相手にマイナスの印象を与え、その後にポジティブな印象を強調することで、感動や喜びを引き出す心理効果として、一般的に広く知られています。しかし、実際には、以下の「ゲイン効果」と「ロス効果」を合わせた効果であり、ポジティブな面のみに焦点を当てているわけではありません。
ゲイン効果:初めにネガティブな印象を受けたあと、ポジティブな印象を受けた場合、ポジティブな印象がより強調される効果
ロス効果:初めにポジティブな印象を受けたあと、ネガティブな印象を受けると、ネガティブな印象がより強調される効果
また、ゲインロス効果には何点か注意が必要です。例えば、最初にネガティブな印象を与えすぎたり、過度に使用し過ぎたりすると逆効果になる場合があります。マーケティングなどで活用する際には、他の心理効果と一緒にバランスよく活用し、相手に計算された演出と感じさせないように心がけると良さそうです。
参考文献
香月勝行・妹尾武治・分部利紘 (2019)『売れる広告 7つの法則 九州発、テレビ通販が生んだ「勝ちパターン」』光文社
良い警官・悪い警官『Wikipedia the free encyclopedia』(最終閲覧日2024年1月10日)
林伸二 (2006)『第一印象の形成』青山経営論集 第40巻 第4号