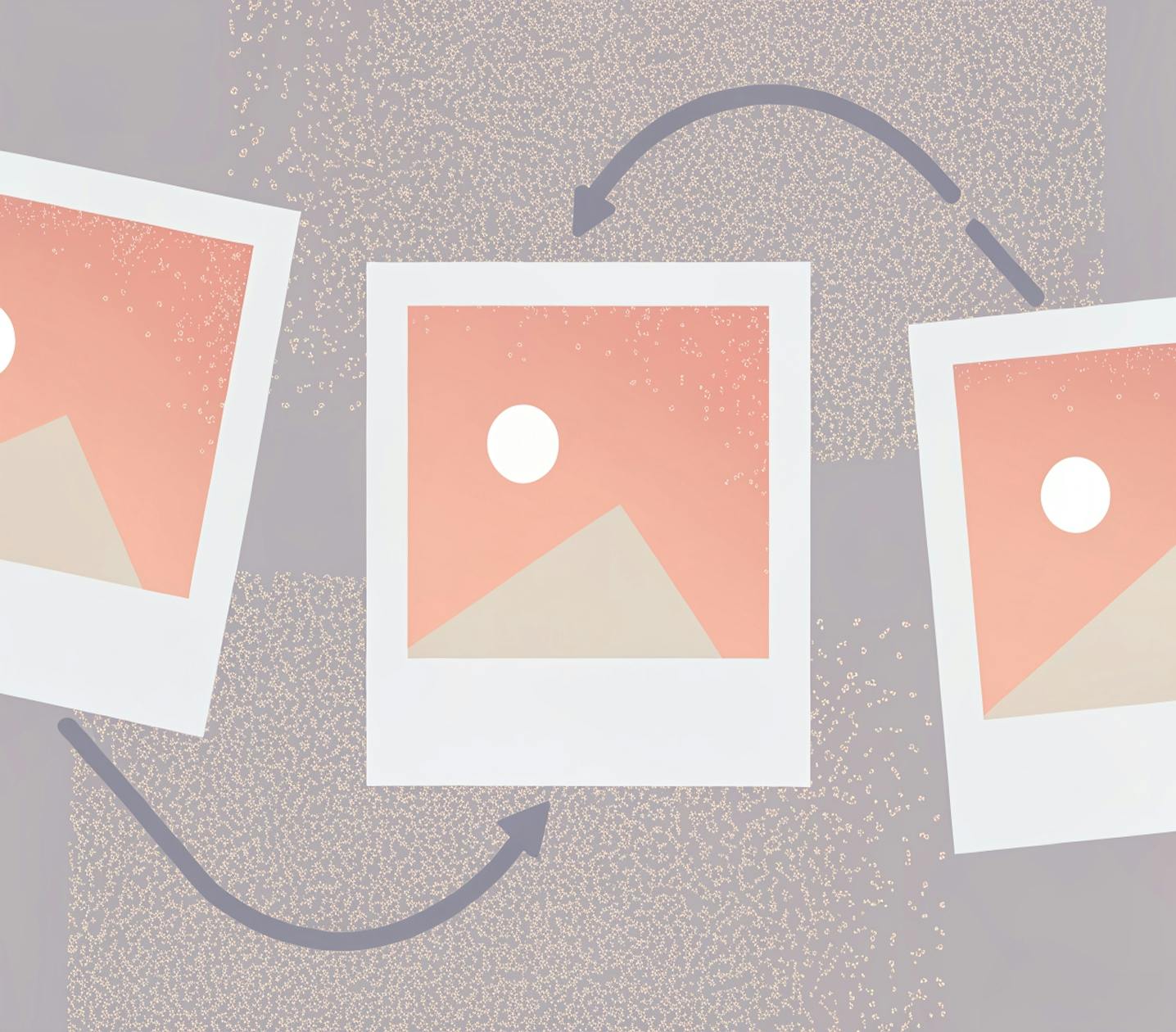新聞をおよそ20年ぶりに取り始めましたが、とてもいいです。何が良いって、「誤配」があること。もちろんちゃんと間違わずにポストに配達してくれるのですが、「情報の誤配」があります。ふだん過ごしていたら出合えない情報が手に入る。SNSなどで自分の興味のある情報にしか触れにくくなる「フィルターバブル」が嫌になったり、アイデア出しに行き詰まったりしている人には新聞をおすすめします。
テレビ、ラジオニュースに感じていた違和感
私が「新聞をとろう」と思ったきっかけは、テレビとラジオニュースへの違和感でした。職業柄、多くの書籍・雑誌、Webメディアの記事やネットニュースは目にしますが、自宅ではテレビ(popIn Aladdin 2)でニュースを見る習慣がありました。
ヘッドラインだけまとめているような、考察がない、深さがない印象。もちろん制作者の方は時間内におさめる苦労があったり、いろんな政治的配慮があったりするんだろうなあと察するのですが、物足りない。
また、なるべく食事のときにはテレビをつけないようにしているのですが、朝は時間がないので情報がほしく、ニュースを見ていました。
ただそうすると子どもが画面に気を取られて箸が進まなくなる。
今度は耳から情報を仕入れようと、ラジオアプリ「radiko」からBluetoothスピーカーで聞くスタイルにしたのですが……某公営放送でも、求めていない野球の球種の話とかを詳しく聞くはめになり(それが知りたい人がいるのも分かりつつ)何か違うな、と。
そこでようやく新聞に至るのでした。
今の時代にこそ新聞を読む意味がある

小さな頃は実家で父親が新聞をとっていて私も読む習慣がありました。20年以上前に大学入学で上京してからも、謎の販売所のお兄さんに「洗剤を2つオマケするよ!」といわれて一度新聞をとっていたことがありました。ただ読む時間が取れず、ゴミになる一方でやめてしまった(洗剤はありがとうございました)。
ただ、今の時代にこそ新聞を読む意味はあると考えます。
情報の「誤配」がある。
冒頭にも書きましたが、今はXやInstagram、その他SNSにネットニュースに……Cookieなどの追跡技術、アルゴリズムで提案された情報が目に入りやすい時代です。罵詈雑言や自分がフォローしたくない情報は必要ないと言えばそうなのですが、一方で見える世界が狭まる「フィルターバブル」に陥りがちです。
外山滋比古の『思考の整理学』などにもあるように、新しいアイデアは思わぬ知識同士がつながるセレンディピティ(偶然の出会い)から生まれたりします。
その点、新聞を読んでいると最近読んで印象に残ったものだけピックアップしてもこんな情報に出合えます。
老若男女の読者の声。「板書を丸写ししたほうが点数が高いテストがあると憤る16歳」「『もっとぴょんぴょんしたい』8歳児」「『後期高齢者』に代わる名称『高齢者のベテラン』を思いついた65歳」の意見。
『機動戦士ガンダム』の富野由悠季監督が警鐘する「若い工学者の『健康体の不見識』」
訃報。大好きな作家、ポール・オースターが亡くなったことを訃報欄で知り『ムーン・パレス』を読み返しました。
社説や国際情勢、経済ニュースは言わずもがな、今まで自分が仕入れられなかった情報に出合えるようになりま��した。思想家の東浩紀さんがいわれる「誤配」が起こりやすい。
- 誤配とは?
- 批評家・株式会社ゲンロン創業者の東浩紀氏による「誤配」=自分のメッセージが本来届くはずではない宛先に届いたり、間違って伝わったりすること。あるいは、知らないでもよかったことをたまたま知ってしまうこと。東氏は『存在論的、郵便的』『弱いつながり 検索ワードを探す旅』『哲学の誤配』など自身の著書を通じて誤配をポジティブにとらえます。
正確性の高いキュレーションメディアである
新聞こそ最強のキュレーションメディアだと思います。記者はプロなので、情報の裏付けも正確(なはずです)。たとえば政党交付金の改革や、円安についての解説についても深さがある。ネットニュースやテレビのニュースの多くはロイターや共同通信などを通じて送られるニュースの速報ベースから起こすものも多いですが、新聞は独自取材も多くあります。
「フィニッシャビリティ」がある
『アナログの逆襲』という本の中で『エコノミスト』副編集長のトム・スタンデージが若年層においてデジタル版より印刷版の部数が伸びた理由をこう語っています。
スタンデージは、『エコノミスト』の印刷版が部数を伸ばしたのは、彼が「フィニッシャビリティー」――読者が最後まで読み終えられること――とでも呼ぶもののおかげだと感じていた。雑誌には明確なはじまり、中間、終わりがあり、読者は終わりに到達すると大きな満足感を覚える。「われわれは、最後まで読み切ったときに自分が賢くなったと感じる、その感覚を売っているんだ。いわば読了のカタルシスだね」と、スタンデージは言う
デイビッド・サックス『アナログの逆襲』186p 加藤万里子訳/インターシフト
読了のカタルシスとは言い得て妙です。新着、関連記事……と構造上はずっと読み続けられる一方で離脱もしやすいデジタルメディアに比べて、紙のメディアは自分のペースで読みやすく、自分がどこまで読んだかすぐに残りの厚みで分かる。それを読み終えたときに不思議な満足感があります。

健康にも良い(はず)
新聞にはバックライトがあるわけじゃないので、少なくともスクリーンを見続けるよりは目には優しいはず。ゴミがたまるのがデメリットといえばそうですが、廃品回収に出すために運動の習慣にもなるはずです(私はそうとらえています)。
家族の会話が起こりやすい
家族で新聞を読んでいると、ふだん話しにくい政治や経済の話も前提情報があるので、話しやすくなってきました。子どもも��新聞の中にある子ども向けクイズコーナーなどを通じて、漢字に触れる機会が増えてきました。
良いアイデアには、まず良い「仕入れ」を
新しいアイデアをまとめるにはまず良い「仕入れ」が必要です。自分で人に話を聞いたり、足を運んだりといった一次情報は間違いなく大事。
でも自分の足を運べない、二次情報は良い仕入れができる人に任せたほうがいい。そういう意味で、新聞は良い情報の仕入れ先なのです。
さらに20~30万字程度の情報が、自分が詳しくないジャンル情報も含めて毎日届くわけです(プランによっては夕刊+デジタル版も)。これで4,000円台というのは、お得に感じませんか。
新聞業界からの回し者というわけではないのですが、アイデアの仕入れ先として新聞購読は一つのヒントではないかと思っています。
Web編集者・ライター、マーケター。株式会社TOGL代表取締役。オンラインもオフラインも編集しており、兵庫県尼崎市武庫之荘でつくれる本屋「DIY BOOKS」を運営しています。